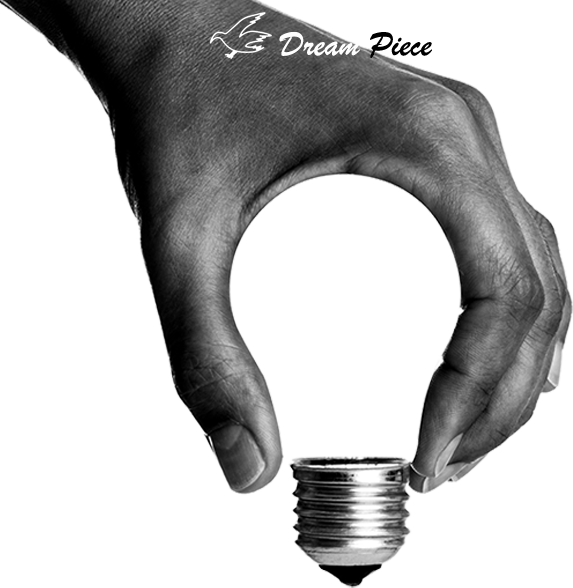もう一人の湊
立ち並ぶ多くの建物は、団地としての風貌を色濃く出していた。それぞれの住棟には四十年以上の歴史が刻み込まれ、古びた風情を持っていた。
各住棟の前には、狭い道が伸びており、そこの住人たちは、その道を進みバスの停留所へと向かい、団地の外の世界へと旅立っていく。
谷地下台団地の九号連の一室で、湊は夢の中に沈んでいた。部屋の内装も外観と相違がなく、歴史を感じさせるものであったのだ。現に彼を包み込んでくれている布団は煎餅のように薄い様相であった。
土曜日で、湊の会社も休日のため、いつまでも眠りの世界を楽しむことが出来たのだが、それを許さないとばかりに、目覚まし時計がけたたましい音を鳴らし始める。それに応じるように湊は目を見開き、横になりながら目覚まし時計に手を伸ばすと、その頭を叩く。
湊が掛け布団を蹴り上げると、布団は宙を舞い、部屋の片隅へと落ちていく。布団から解放された、彼は勢いよく立ち上がると、大きく背伸びをする。四月の朝の寒さを感じ、湊は腕を体の前で組んで身を縮こまらせた。一瞬、彼は再び布団に身を委ねようかと考えたが、すぐにそれを拒絶する。夢の世界への入り口が、彼をもう一つの恐ろしい世界へと引き込む原因になるかもしれないと感じていたからだ。
先週の土曜日、湊は《力の世界》と呼ばれる別世界の自分たちと戦った。相手は、別世界の彼自身と悠太、後は見知らぬ中年の男性が二人いた。
湊はその戦いに勝利を収めたものの、自身の格闘能力に失望したのだ。湊は戦うことを望んではいなかったが、相手の矛を止めるのにも力は必要だと感じ始めたのだ。そのため、湊は最寄り駅の谷地下台駅にあるボクシングジムに、幼馴染の悠太と通うことを決意した。暴力の嫌いな彼としては、それは一大決心である。
湊は部屋の真ん中にある、木でできた背の低い机に視線を移し、その上に存在するアンパンを食べに向かう。その横には水が入ったコップもあった。昨夜に、彼自身が飲みかけた物だろうが、湊はそれを口に近づける。すると、生ぬるい温度が、彼の口の中に飛び込んできた。次にアンパンを口に入れると、甘いあんこが口の中に広がった。
空腹を満たした湊は、瞳を左右に動かす。そこに広がっていたのは、湊が普段から見ている風景であった。古い家具に、しみだらけの壁。その中には安物の家具が置かれていた。まさしく、貧しさを象徴している部屋と言えるだろう。彼は勤務先の会社自体に不満を持っているわけではなかったが、生活の質を上げたいという思いはあった。
ただ、何故、独り暮らしの湊が、このような、広い部屋を借りる必要があったのだろうか。間取りも2LDKで一人暮らしには持て余すように思えた。彼は引っ越し時の記憶が薄れてしまっていたが、都内に比べれば、賃料が安いから広い間取りを好んだのかもしれない。
湊の考えが深まってくると、玄関の方からインターフォンの音が聞こえてくる。その音に彼の思考は現実に引き戻される。恐らくは、幼馴染のオリビアが迎えにきたのだろう。
オリビアは学生時代の頃から湊を迎えにきていたが、当時から、彼女をよく待たせたものである。彼は申し訳ない気持ちを持ちながら、足早に玄関に向かうことにする。
湊が玄関に着き、出入り口の扉を開けると、そこにはオリビアの姿があった。彼女の金色の髪が、朝の光を受けて、一層綺麗に輝いていた。そして、その清らかな彼女の顔に合わせたように、白いワンピースを着ていた。幼い頃、湊がその服装を褒めて以来、彼女はその服を好んでいるようであった。
オリビアの顔には優しい笑みが浮かんでいた。それが現れる度に、湊の心は弾んだが、次第にその笑顔は、苦笑いに変わって行く。
「まさか、また寝ていた?」
薄めの化粧が施され、外出準備が整っている彼女に対し、湊がジャージ姿のためだろう。彼女は他の人間には遠慮がちに話すが、彼に対しては無遠慮で話すことが多かった。ただ、それに湊が不快感を持つことはなかった。オリビアが彼だけに見せてくれる顔は、湊に心地良さを与えてくれるのだ。
「ごめん、ごめん。たださ、ジムに行くんだからジャージで良くない?」
湊が苦笑いを浮かべながら言うと、オリビアがため息を吐き出す。
「でも、外出するにはどうなのかな?」
オリビアが湊の頭を指差す。恐らくは、彼の頭には、立派な寝癖が出来上がっているのだろう。くせ毛の彼の頭にとっては、寝起きの髪型は難解なものになる。ただ、身だしなみにこだわりを持たない湊にとっては、その難解を解決する意思はなかった。
「まあまあ、行こうよ」
湊は玄関に並んである靴を履き、オリビアの横を通り抜けて外へ出ていく。彼が外に出ると、部屋の扉がゆっくりと閉ざされていった。
「鍵は閉めないの?」
「何のために?」
湊には、鍵を閉める理由が理解できなかった。他人の家に侵入し、何をするというのだろうか。
「閉めて」
オリビアの叱責に従い、湊は玄関へと足を戻し、靴箱の上に無造作に置かれている鍵を手に取る。再び、彼が玄関の外に出ると、ゆっくりと玄関の扉が閉ざされ、湊は鍵を閉めることにする。
湊とオリビアは建物の前にある狭い道に向かう。彼の住居が一階であることから、すぐに外界の風景が湊の視界に入ってくる。
外界に出ると空に存在する太陽の恵みが湊達を照らしてくれる。朝の春の風は、未だ肌寒さを感じるものの、冬に比べれば、優しい気温になってきたように思える。
二人は建物の前にある狭い一本道を歩き、バスの停留所に向かうことにする。駅前に行くのに時間を要するのが、この団地の大きな欠点であった。
二人が狭い道を歩いていると、オリビアが湊に視線を向けてくる。
「でも、戦いのために、ボクシングを習うなんて貴方らしくないよ。何のために鍛えるの?」
「暴力を止める力が欲しいんだ。相手に危害を加えるために鍛えるわけじゃないよ。止めるため」
湊も人に暴力を振るうことが悪いこととは理解している。しかし、その一方で、彼が戦いを止めようとしても相手の暴力に晒されてしまうのだ。前回、対峙した力の世界の自分は大きな腕力を携えており、その力は、湊達を危険に晒すことになった。それを制するだけの力が求められているのだ。
「前回の相手の人達の世界は消えちゃったのかな?」
オリビアの言葉は彼女らしく、優しいものだった。湊も心を痛めていたが、勝利を譲って自分たちの世界を消すわけにはいかない。そのため、湊には両方の世界を守る方法を模索する必要があった。そうでなければ、湊たちの戦いを止めようとする提案も、ただの絵に描いた餅に過ぎないだろう。
湊たちが狭い道を左に曲がると、バスの停留所に通じる広い道が目の前に広がった。そして、その先には、低い柵で囲まれた公園の姿が見えてき、そこから、子供達の笑い声が聞こえてくる。ブランコ、ジャングルジム、砂場、彼らが子供たちの相手をしていた。その様子を見て、湊が優しい笑みを浮かべる。
この公園は、幼い湊がオリビアと遊んだ想い出の公園だ。ここを通る度に彼には懐かしい感情が込み上げてくる。ここで、時間が止まってくれれば、オリビアと一緒にブランコに乗るのも悪くないだろう。しかし、今では子供達が、公園の遊具たちと戯れている。大人である湊たちは、彼らの邪魔をしないように目的地に向かうのが正解だろう。
湊たちがしばらく歩を進めると、やがてバスの停留所の姿が視界に飛び込んでくる。平日の朝は賑わうものの、休日の今日は静けさを保っていた。
湊たちが停留所に到着すると、そこには屋根と椅子だけが存在していた。彼はオリビアに椅子に腰掛けるよう促す。彼女はゆっくりと腰を椅子に下ろし、湊に視線を向けてくる。
「湊も座りなよ」
オリビアの提案に応じて、湊も彼女の隣に腰を下ろした。すると、彼の腰に冷たい温度が伝わって来る。
二人でバスを待っていると、湊の心には学生時代の思い出が浮かび上がってきた。今も幸福な人生を送れている彼だが、かつての思い出も彼にとっては輝かしい宝物となっていた。
「貴方の事だから心配無用だろうけど、ジムで力を付けても、極力、使わないようにね」
「うん。俺らの世界と他の世界を守るために使いたいんだ」
湊は世界を守るという重圧に押し潰されそうになる時があった。オリビアや悠太を始め、この世界の人々を守りたいという気持ちは日に日に強まっていた。子供の頃に憧れたヒーローのように問題を解決できればと思うが、現実には湊はそんなスーパーヒーローではない。
湊がそんなことを考えていると、車の排気音が響き渡ってきた。そして、大通りの先からバスが姿を現す。それは彼らの目の前まで進んできて、ゆっくりと停車する。
バスの扉が口を開けると、二人は静かに立ち上がり、中へと足を踏み入れて行く。このバスにしばらく乗れば、最寄り駅の谷地下台駅に到着するだろう。
湊たちがバスの中に足を踏み入れると、多くの乗客が座っていたが、偶然にも横並びの二つの席が空いていた。湊とオリビアは導かれるように、空いている席に腰を下ろす。二人が着席すると、バスの扉がゆっくり閉まり、バスの大きな身体が動き出す。しばしの空白の時間が流れるため、湊は魂力に考えを巡らせる。
魂力は魂が肉体から離れると、大きな力を発揮する。そして、自らの魂に合う力を願うことで、多大な効力を期待できるらしいのだ。例え、湊が身体能力を鍛えたとしても、自分に合う魂力を見つけなければ本当の意味での力を得ることは出来ないことになる。争いを止める力。もし、湊の魂にそのような力が備わっていれば、ありがたいことだろう。
湊が思考の世界に入り込んでいると、バスが停止し、入口の扉が口を開ける。そして、その扉から、一人の老人がゆっくりとバスに足を踏み入れてくる。
湊が首を左右に動かすと、優先席に若者が座っていたが、彼には全く譲る意思がないように思えた。そして、次に窓際に座っているオリビアの方に視線を向けると、老人に手を向けていた。恥ずかしがり屋の彼女のことだ。声をかける決心をするのに時間がかかるのだろう。代わりに湊が勢いよく立ち上がる。
「良ければ、ここに座りませんか?」
オリビアに先んじて、湊が老人に声をかける。
「ありがとうございます」
老人は礼を告げた後、弱々しい歩みで進んでいき、湊が座っていた席に座る。優先席に座っている若者は居心地が悪そうな顔をしていたが、湊は彼を責める気にはなれなかった。恐らく、席を譲ろうと思ったものの、声をかけるのが照れくさかったのだろう。
「湊・・・。ありがとう」
オリビアが顔を伏せ、か細い声をあげる。困っている者がいれば手を差し伸べるのは、彼にとって自然のことであった。オリビアも席を譲ろうとしていたが、湊が先走ったに過ぎないだろう。幼馴染のオリビアや悠太はどちらも人格者であり、湊は彼らに尊敬の念を持っていた。
「次は谷地下台駅前・・・」
しばらくすると、バスの運転手が谷地下台駅到着を告げる合図をしてくる。
「じゃあ、私はユアーデイズで待っているね」
オリビアが声をかけて来る。
ユアーデイズは谷地下台を象徴するようなデパートだ。湊がボクシングの練習をしている間は、彼女はそこでの買い物の楽しみに浸るのだろう。