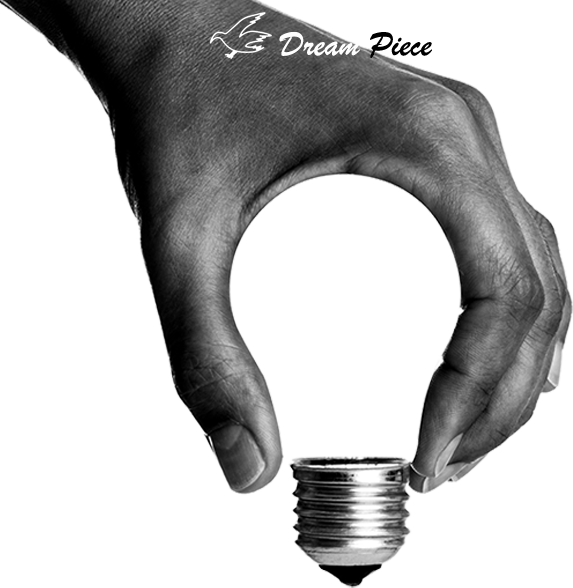狂気
空は漆黒の色合いに変貌し、雲が月の光を隠していた。その雲はまるで湊の心境を語るように、雨という名の涙を天から地上に零していた。
教会の周辺は森林が広がっており、風の息吹に踊らされていた。湊は傘を差しながら、その教会の前で立ち尽くしていた。
リアムからの呼び出しに応じて船橋の教会に来たものの、湊の胸の中には不安な気持ちが渦巻いていた。そのため、足が一歩も進まなかったのだ。
しかし、立ち尽くしているだけでは物事が解決する訳がない。湊は深呼吸をし、教会の重々しい扉をゆっくりと開ける。
湊が教会に足を踏み入れると、暗黒に包まれた聖堂が広がっており、奥の机にある蝋燭だけが僅かに光を放っていた。そして、その光の放つ元にはリアムの姿があった。
湊はその姿を目指し、ゆっくりと歩き始める。聖堂の異質な空気が彼の身にまとわりついてき、足に重りがついているように感じていた。
湊がリアムの前まで距離を縮めると、彼はゆっくりと顔を上げてきた。その瞬間、天からの怒りのような雷の音が鳴り響き、聖堂を明るく照らした。
「貴方こそ、僕が求めていた人だ」
リアムは以前から何者かを探していた。彼が求める存在とは、本来であれば人が交われる存在ではない。その人物を追い求めるだけで、正気を疑われるものだ。
「貴方は神だ。僕たち人間たちを導くね」
リアムの目は正常の者が持つ類ではなかった。焦点は合っていなく、不気味な笑みを浮かべていた。その狂気の顔から、彼が何を考えているのか読み取ることはできなかった。
「何を言っているの? 冷静になるんだ。俺は人間に過ぎないよ」
「君は創造したじゃないか? 物を、そして、新たな生物を」
確かに、湊が様々なものを生み出してきたことは事実だろう。しかし、それは単なる魂力に過ぎない。
しかし、湊は思案する。彼の魂力は人の域を超えている。神の所業かと問われれば否定はできないだろう。しかし、湊は神のような全知全能の存在ではない。
「確かに、俺にはそんな力があるかもしれない。けど、それだけで神なんて名乗れないよ。世界を生み出した方なんでしょ?」
「君もやろうとしていないだけで、出来るんじゃないか?」
「馬鹿なことを」と湊は心で呟く。人が世界を生み出すことなんて出来る訳がない。しかし、現在は並行世界が生み出されているのは事実だ。しかも、それは全知全能の神の行いとしては、あまりに稚拙なものであった。
「人の文明は素晴らしい。彼らは発展を遂げてきた。ただ、それと同時に神を忘れてしまっている。我らを作り給うた偉大な存在を。だから、神の子の僕は神を探していた。そして、それが、貴方だ」
湊の背筋が冷たくなる。リアムは完全に狂っていた。
「完全な妄想だ」
「貴方は、神を忘れたこの世界に満足しているのか? 正しいと思っているのか?」
リアムの言葉に、湊はうつむいて、思考を巡らせた。彼の問いに対する答えは明白だった。
親友の悠太の魂は失われ、職場では奴隷のように使われている。かつて湊だけを見ていたオリビアも異なる人物に変わりつつあった。こんな場所よりも理想的な世界があるかもしれない。
金、力、恋、権力、見栄、この世界を知る毎に、湊の心は重くなっていくばかりだ。昔の彼自身のように純粋に楽しめる世界が存在すれば、どれだけ心が安らぐだろうか。
リアムは湊の沈んだ表情を見つめ、穏やかに声をかけてくる。
「さあ、貴方の理想の世界に近づくように、人々を導いていこう」
湊の思い描く理想の世界、それはオリビアと共に幼き時代に生きることではないだろうか。あの頃の日常は純真で、宝石のような輝きを放っていた。
しかし、オリビアは言っていた。「時は戻らない」と。過去を甦らせるような手段で得られた時間は本物とは言えないのではないだろうか。決して、人は神にはなれない。人がそのような者になることを望めば、今のこの世界のように歪みが生まれるように思えて仕方がなかった。
「やめとく」
「なぜ?」
リアムが口を開け、目を大きく見開いていた。その声には驚きと疑問が込められているように思えた。
「人は神にはなれない。神としてではなく、俺は人として幸せになりたいんだ。その幸せは、魂力なんかで得られるものじゃない。君も魂力に溺れずに生きて欲しい」
湊は自らの手を見つめて、その力の意味を問うていた。そんな彼の姿に向けて、リアムが観察するような視線を向けてくる。
「それが、貴方の答えか?」
リアムが呟き、無言で湊を見つめていた。その瞬間、彼の額から冷たい汗が溢れて落ちき、心臓は高なっていった。
しかし、突如、リアムの表情が和らぎ、彼がよく見せる優しい笑みに戻る。
「はははっ、冗談だよ。びっくりした?」
リアムの突然の大声に、湊の身体が震える。喉から心臓が飛び出してくるところであった。
「君が望むなら、そうしよう。僕にとって、君の言葉が全てだ。君が望むままに」
リアムの瞳には優しさの中に狂気が混ざっているように思えた。その不可思議な瞳が、湊に不吉な予感を感じさせた。