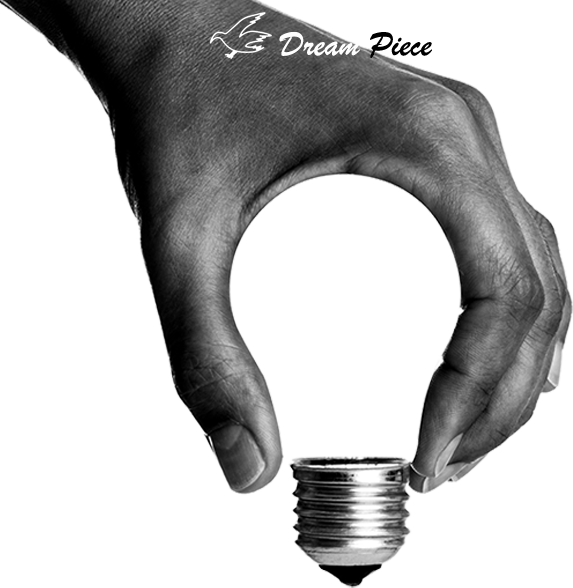リアム・ジョンソン
木々が風に揺らされていた。そして、木々に守られるように、中心にはゴシック様式の洋風な建造物が建っていた。白い外壁にオレンジ色の屋根。それは、日本では珍しい建造物だろう。
船橋の教会は、湊の目の前にある建物で間違いないだろう。ただ、教会への訪問が初めての湊の心は緊張に支配されてしまっており、建物の前で立ち尽くしてしまっていた。
しかし、いつまでも立ち尽くしているわけにはいかない。湊は深呼吸をして決意を固めた。そして、教会の扉へと歩を進め、その重厚な扉をゆっくりと押し開けると、鈍い音と共に扉がゆっくり開いていった。
湊が教会の中に足を踏み入れると、そこには、多くの椅子があり、奥には机が存在した。その様相は日本の建造物とは一線を画しており、彼が映画などでしか見たことがない《聖堂》がそこには存在していた。
湊が見た映画の中では、人々が椅子に座り、祈りを捧げている印象があった。しかし、この聖堂には人々の姿が存在しなかった。
「どなたかいらっしゃいませんか!?」
湊が大きな声を上げると、奥から扉がゆっくりと開かれ、司祭のような装束をした初老の男性が現れた。白いローブをまとい、白髪の上に小さな帽子を乗せている彼は、机の前まで歩いてくると、湊に視線を向けてくる。その男のしわの刻まれた顔には、優しい笑みが浮かんでいた。
「私はここの司祭です。君は入会者かな?」
「いえ、先ほど、本の落とし物のことで連絡した者です」
「ああ、落とし物を拾ってくれたとか。今時、感心な子だな。リアムもそろそろ来る頃だよ」
金髪の男の名前はリアムというらしい。確かに、彼の顔の造形は欧米系の血が混ざっていることの証明と言えた。
「さて、君はシン教に興味はないかな?」
司祭の言葉に、湊は顎の下に手を置く。
湊は宗教とは縁がなかったが、それは彼が興味を持っていなかった訳ではない。今、湊は神を中心とした戦いに身を置いている。この機会に宗教の見識を深めるのも悪くないだろうと思ったのだ。
「ええ、興味あります」
「では、入会書を用意するんでな。入会費の事もそこに書いておるから」
費用の話が出てきたことで、湊は肝を潰した。彼はズボンの後ろポケットに入れている財布が気になりだす。今月は財布にどれだけの余裕があるのだろうか。
司祭が入会書を取りに行くため、机から移動を始めようとするが、突如、湊の背後から鈍い音が聞こえて来る。
湊が音に反応して振り返ると、そこには扉を開けている金髪の男が存在していた。後光が彼の美しい姿を際立たせ、その姿は神々しく思えた。
「司祭様。申し訳ありません。《経典》を落としてしまい・・・。今まで探したのですが、見つかりませんでした。神様に顔向けができません」
「神の子のお前にはあってはならないミスだな」
司祭が厳しい眼差しでリアムを見つめると、彼が深くうなだれる。リアムのその様子に、湊の心は心配になってくるが、突如、司祭の顔が緩む。
「ははっ。冗談、冗談。経典は、その子が持っとるよ」
司祭の言葉に、リアムは見開いた目で湊を見つめてくる。彼の顔立ちは男の湊が見ても、惚れ惚れとしてしまうような造形であった。
リアムは、ゆっくりと湊の方へ歩み寄ってきた。そして、彼の手を握ってくる。なぜか、湊の胸が高まり、頬が僅かに紅潮してしまう。
「貴方が届けて下さったのですね。ありとうございます」
「いえ、俺こそ、勝手に持ってきて、すみません」
それは湊の本心から出た言葉であった。彼が持ち出さなければ、リアムは自らで落とし物を取り戻せていたかもしれなかったからだ。
「いえいえ、悪人に取られていたらとんでもないことでした。貴方は僕の恩人です」
「そんなに畏まらないで。歳も近そうだし」
「そうなんですね。貴方のご年齢は?」
二人が年齢を明かすと、同い年齢であることが分かる。その事実を知ったリアムは目を細めた。その表情は無邪気な子供のような純粋さを携えていた。
「同い年ですね。出来たら、以後、敬語はなしでお願いできるかな?」
湊も敬語は得意ではないため、その提案に同意する。
「貴方のお名前をお聞きしても? 僕の名前はリアム・ジョンソン。恩人の名前を知りたいんだ」
「小林湊だよ。でも、恩なんか感じなくていいよ」
それも湊の本心からの言葉であった。湊にとって、落とし物を届けるのは当然のことで、特別に感謝されるものでもなかった。
「今後、恩人様は私たちの仲間になるんだよ。今後とも仲良くしてくれ」
司祭が嬉しそうな表情を浮かべていた。余程、入会者がいないのかもしれない。司祭の満足そうな笑顔に、リアムは苦笑いをしていた。
「まさか、入会費を取ろうと言う魂胆じゃないでしょうね」
「当然だろ?」
司祭は怪訝な表情をしていたが、それを聞いたリアムが眉をひそめる。
「無理やりじゃないでしょうね? 教義は素晴らしいのに、教徒が少ない理由はそれですよ」
「何を言っておる。彼の意思だ」
「なら、入会費は僕に払わせてください。献金も僕が払います」
「誰が払ってもいいよ」
リアムと司祭の会話を耳にし、湊の心は揺れていた。支払いを行えば、彼の財布は火を吹くかもしれないが、湊の負担をリアムに押し付けるよりかは幾分かは心が楽になるだろう。
「いや、悪いよ。それに、まだ入会するか分からないし」
「これも縁だよ。君が気に入ったなら、今後は払ってくれればいい。検討している間は、僕に払わせて欲しい。君みたいな純粋な人が入るべき宗教だよ。司祭はあんなだけど、素晴らしい宗教なんだ」
リアムの言葉に、司祭が仏頂面を浮かべていた。
「でも・・・。そんな事をしてもらうわけには」
「あ、もちろん、無理強いする気はないよ。検討して欲しいだけなんだ。ただ、それとは関係なく、僕と友人になって欲しいんだ。君とはもっと話したい。連絡先を教えて」
リアムがズボンのポケットに手を入れたかと思うと、そこから、スマートフォンを取り出す。