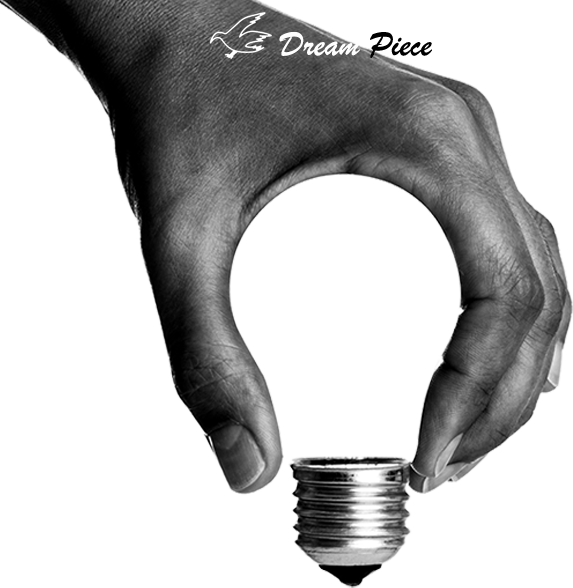神楽にとっての颯真
まるでリゾートの様な孤島があった。そこを囲む様に広がる海達には生命が存在していた。そうは言っても、純粋な生命ではない。それは、スプライトと呼ばれる人工生命体だ。
ただ、地球の時の様にスプライトで特殊な生物を作るつもりはなかった。この星は地球と同じ運命を辿らせる予定なのだから。ただ、地球とは違い、人々が永久に繁栄していく物語にして行きたい。人は賢く美しいのだ。きっとできるはずだ。
そんな事を考えながら、神楽は孤島の浜辺に歩いていた。そこには、いつもの様に颯真が居た。神楽の目的に既に彼は不要だろう。あとの詰めの部分は牡丹にでも出来る。
神楽が颯真の横に座ると、彼がこちらに視線を向けてくる。
「不老不死の身体には慣れたかい?」
颯真が興味無さそうに声をかけてくる。今の身体は生身では無い。不本意ではあるが、この星の行末を見守るためにも悠久の時間が必要だったのだ。
「あんた程の賢い人がそんな物を望むとはね。神にでもなんの?」
「不老になる事は目的では無く手段ですよ」
神楽の言葉に颯真は返答すること無く懐から写真を出す。そこには、リーナが写っていた。
「貴方はリーナさんを愛していたのですか?」
「当たり前だろ?」
颯真は微笑していたが、神楽は疑問に思っていた。赤い結晶の代償は愛する者の命だ。それであれば、リーナは既に死んでいないとならない。ただ、少なくとも最後に会った彼女は病問題を抱えていたが生きていた。
「私を恨んでいますか?」
「あんたを恨んだ事なんか一度もないよ。ただ、離れてから、よくリーナの事を考えるんだ」
颯真が写真から視線を変え、海の先に視線を向ける。それは、遠い星のソマリナの事を考えているのかもしれない。
颯真とリーナを引き離したのは正解だったと思っていた。少なくとも彼が彼女の事に思い悩まなくとも良くなると考えていたのだ。
颯真にとってのリーナは負担だったのでは無いだろうか。もちろん、好意が合ったのは間違いないのだろうが、二人の考え方は違いすぎた。
「赤い結晶の代償がある限り、貴方はリーナさんの事は忘れた方がいい」
「ああ。あんたに話したっけかな。まあ、どうせ、俺はソマリナに行く事も無いしね」
颯真はそう言いながらも、複雑な表情をしていた。それには、後悔、悲しみ、怒り。様々な感情が混ざっている様に思えた。
「いえ、私の目的は、ほぼ叶いました。もう貴方はソマリナに行くといい」
それは本心からの申し出だった。颯真にはリーナが必要だったのだ。例え、それで二人が不幸になろうとも一緒に居させてあげるべきだったのかもしれない。
「多分、もう間に合わないさ」
「何が? フリーエネルギーの宇宙船ならば五年位で着くでしょう? 呪いがリーナさんを蝕んで、間に合わないと言いたいのですか?」
「いや、違うさ。俺の寿命が尽きるからさ」
一瞬、神楽は意味を理解できなかった。リーナでは無く、颯真の命が尽きようとしている理由が思い浮かばなかったためだ。
だが、神楽はある考えに思い至る。颯真は二度、赤い結晶の魔法を使ったと言っていた。
「まさか、赤い結晶の力を使うために自身の寿命を代償にしたとか言わないですよね?」
「正解だ」
「馬鹿な事を!」
神楽は思わず大声を上げてしまう。そんな事のために寿命を捧げるなんて、あまりに非合理的だ。ただ、目的と手段が逆だったなら納得できる。
「捧げといて良かったよ。ただ、予想外に長く生きれてしまった。後、どれくらい生きるのだろう」
「貴方にも不死の身体が必要かもしれませんね」
神楽は立ち上がる。そう、颯真も自らと同じ身体を持てばいいのだ。そうすれば、赤い結晶の呪いから逃れる事が出来るかもしれない。その事を研究室にいる牡丹に告げなければならない。
「待ってくれ。これを受け取ってくれ」
神楽が颯真に背を向けると、声をかけてくる。ゆっくりと、彼は立ち上がり、黒い鉄の塊を神楽に渡してくる。それは、明らかに拳銃であったが、これを何のために渡してきたのだろうか。神楽に嫌な予感が浮かび上がってくる。
「離れたら、俺の脳裏から消えると思ってた。でも、ダメなんだ」
「一人の女性のためなんかに、貴方が命を投げ出す必要は無い。貴方の命の価値はそんなに安くない」
「いや、もう、今すぐに俺を消去してほしいんだ」
神楽の言葉を無視する様に颯真が言うが、何のために、人類の財産と言うべき男を消さないとならないのか。いや、自らが動揺しているのはそれだけの理由だろうか。
「あんたが無理なら、俺は地球に行くしかないんだ」
それは自ら死にに行く行為である。魔物も権力も持ち合わせない彼が地球に行けば、魔力で死に絶えるのは目に見えている。罪悪感から自己犠牲をするなんて馬鹿らしい事を颯真がするとは思えない。自らの命を捨てたい。その想いがある様に思えた。
最早、神楽が何を言っても、何を行なっても無駄だろう。颯真が言う事を聞くとは思えない。地球で野垂れ死ぬか、ここで、何かしらの方法で命を落とすのだろう。それであれば、心が通じ合える人間が出来る事は何であろうか。それは、綺麗な最後を迎えさせてあげることではないだろうか。そして、彼の願いを叶えてあげる事こそが花向けになるのではないだろうか。
神楽は自らの不甲斐なさに歯軋りをしながら空を見つめる。